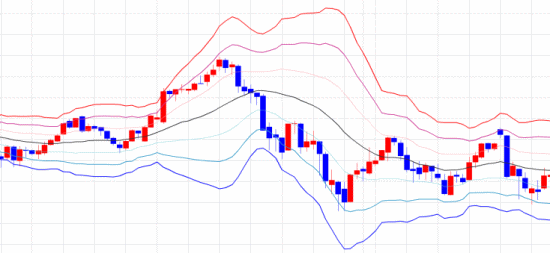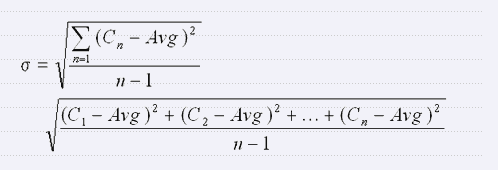私は「テクニカル分析」において、また、その際に用いるテクニカル指標などについては、その「理論」や「成り立ち」といった『背景』を、まず何よりも重要視するようにしています。
| ここで言う『重要視』というのは、まず、それらを「知り」、そして「理解する」という事で、その上で、その「有効性」「合理性」などを判断するようにしているという事です。 |
そもそも「テクニカル指標」と呼ばれるものは多種多様、様々なものが存在し、その有効性における判断は、どのようなテクニカル指標でも見解が分かれる余地があるものだと思います。
ただ、少なくとも私は、その「理論」や「成り立ち」といった背景に合理性や有効性を感じられないもの、それらに納得ができないもの、また、それらをそもそも理解できないものには一切、手を出しません。
あくまでも、自分自身がそれらに「合理性がある」と納得できたものだけを頼りにトレード(売買)を行うようにしているという事です。
-私がテクニカル指標の理論、成り立ち、計算式、その背景に重きを置く理由。
実際に「テクニカル指標」を利用しているトレーダーの多くは、チャート上に表示される、それらの指標のみを見て、相場(レート)との相関関係などから、売り買いの判断を下している場合がほとんどです。
ですが、このような「テクニカル指標」と呼ばれるものには、必ず、その背景となるような理論、成り立ち、計算式などが存在します。
つまり、チャート上に表示する事ができる「指標」にあたるものは、そのような理論、計算式を前提とた上での「結果」として表示されているものに他なりません。
ただ、世の中の大多数のトレーダーは、その「理論」や「成り立ち」などを全く理解する事なく、チャート上に表示できる指標のみを、ただ漠然とアテにしている傾向にあります。
どこかのサイトに書いてあった情報、投資関連の書籍、情報商材など書かれていた内容など、それらの「表面的な情報」のみを鵜呑みにして、そういった「指標」を利用しているわけです。
そのようなトレーダーは、当然ですが、
『その指標と相場の値動きに、どのような関係性があるのか』
『その関係性には、どのような理論的な裏付けがあるのか』
『その関係性に基づく判断基準がどういった理由で「正しい」と言えるのか。』
このような「理論的な背景」などを全く理解していない傾向にあり、また、強いて「理解しよう」ともしていません。
その判断基準の「正否」や「真偽」がトレードの勝ち負けを左右し、自らの大切な資金の行方を大きく左右するにも関わらず、表面的な情報のみを鵜呑みにして自らの資金を相場の世界に「投じている」という事です。
| 例えば、以下は実際に多くのトレーダーが利用している『ボリンジャーバンド』というテクニカル指標をチャート上に表示させたものです。
実際に『ボリンジャーバンド』を利用しているトレーダーは、このような形でチャートに表示されたものを「売買の基準」にしているわけですが、この『ボリンジャーバンド』にも、その「理論」に基づく以下のような計算式が存在します。
ただ、実際に『ボリンジャーバンド』を利用しているトレーダーの大多数は、上記のような計算式の存在や、どのような理論でこのような計算式が成り立っているのかなどを、まず「理解」していません。 |
-その「投資行為」に合理性はあるのか。
多くの「テクニカル指標」と呼ばれるものは、それなりの有効性があって世に残っているものがほとんどのため、その表面的な情報をアテにするだけでも、一時的、短期的には勝てる場合もあると思います。
ただ、それだけで継続的に勝ち続けられるほど、相場の世界はあまくありません。
それこそ「テクニカル指標の有効な使い方」にあたる情報は、あらゆる形で世の中に出回っていますが、そういったものをアテにしている大多数のトレーダーは最終的に負けているのが「現実」です。
ですが、彼等が負けている原因は、テクニカル指標そのものにあるわけでも、その使い方にあるわけでもなく『その敗因そのものが分からない事にある』というのが実情だと思います。
そもそも、テクニカル指標を表面的な情報のみを鵜呑みにして売買(トレード)を行っている時点で『自分自身が、そのような売り買いを行った理由』を理論的に説明する事も、まず出来ません。
せいぜい、そこで言える事は『このテクニカル指標がこうなったから買った(売った)』といったレベルの「理由」でしかなく、これは全くもって「理論的な理由」とは言えないと思います。
強いて、それが自分なりの「理由」であったとするなら
『何故、そこで買う(売る)という判断に至ったのか。』
『その判断基準は、どのような理屈で成り立っているのか。』
『指標がそのようになる事とその後の値動きにどのような関係性があるのか。』
このような、そのテクニカル指標と値動きの「関係性」や、それらを紐づける「因果関係」など、これらもしっかりと「理論的」に説明できなければなりません。
逆にこれらを理論的に「説明できない」のであれば、それは、自分自身が自ら行った売買の「背景」や「要因」を、自分自身が、そもそも『よく分かっていない』のと同じです。
そして、自らの売買の理由、要因が「不透明」という状況は、それによって導き出された「結果に対する要因も不透明」という事になり、売買(トレード)の結果がどうであれ、その「敗因」も「勝因」も、結局のところ『分からない』という事になってしまうわけです。
そして、その「敗因」も「勝因」も分からない状況では、いざ負けた時も、勝てた時も「その要因と結果の因果関係」を全く追求できない事になります。
言わば、そのような「因果関係の追求が出来ない事」こそが、指標の成り立ちや背景的な理論を理解しないまま、その表面的な情報のみを頼りにしているトレーダーの大半が「勝てない理由」であり、また「負けてしまう原因」に他ならないという事です。
-何故、負けたのか。何故、勝てたのか。
たとえ、どのような物事においても、物事の「結果」には、必ず、その「要因」にあたるものがあり、それは「投資」や「トレード」においても何ら変わるものではありません。
故に、そのような「結果」が良いものであっても悪いものであっても、その「原因」「要因」を追求していく事が非常に重要であり、
・良い結果を生み出す要因を突き詰める事
・悪い結果を生み出した要因を突き詰める事
この2つを併せて行っていく事で「より良い結果を生み出せる要因の追求」と「悪い結果を生み出してしまう要因の排除、改善」といった方策を実際に取っていく事ができるわけです。
| それこそ、世間的によく言われる「失敗は成功のもと(母)」という言葉は、まさにこの事を言っていると思いますが「成功は更なる成功のもと(母)にもなる」という事です。 |
よって、その物事がどちらに転んだとしても、その「要因」を追求する事は非常に重要であり、とくに投資、トレードの世界では「勝つ経験」と「負ける経験」の両方を嫌でも幾度と体験していく事になります。
だからこそ、実際に勝つ事が出来た際も、負けてしまった際も、常に、その「要因」を徹底的に追及していくべきであり。
「何故、勝てたのか」「何故、負けてしまったのか」
これらを明確にした上で、自らのトレードルールや、その「売買の基準」の精度を、常に向上させ続けるべきなんです。
ですが、世の中の大多数のトレーダーは、自分自身が実際に行った「売り買い」に対して、そのような売り買いを行った「要因(理由)」を理論的な面で「明確」にする事ができません。
これは言わば、その勝因も敗因も「分からない」という事であり、そのような状況では、当然、そこから生じた「結果」に対する「要因」を追求する事も出来ないことになります。
まさに表面的な情報のみを鵜呑みにして指数を用いているようなトレーダーは、その根本的な「売買の要因」を明確にできないため、それらの因果関係を本質的に追及する事も出来ないわけです。
| 故に、テクニカル指標を用いてトレードを行っているトレーダーのほとんどは、自らのトレードの「結果」に対して『何故、負けたのか』『何故、勝てたのか』の要因を追求している「つもり」でも、それを本質的には「全く」と言っていいレベルで行えていません。 そして、そのような「勝因や敗因の追求」を実質的に『放棄』している時点で、そのトレーダーは既に「勝ち続ける事を放棄しているに等しい状況にある」という事です。 |
▼ いわゆる投資関連の「情報商材」「トレードツール」の現実。インターネット上で出回っている投資、トレード関連の「情報商材」などにおいても、そこで提唱されている売買のルールや基準に対して、その「成り立ち」や「理論的な背景」がしっかりと言及されているものは、ほぼ皆無なのが実情です。 『何故、そのようなルールや基準が成り立つのか。』 といった、そのルールや基準における「理論的な背景」などは、まず言及されていない傾向にあり、トレード系の「ツール」などにおいては、売買におけるロジック(基準)そのものが完全に不透明なものも珍しくありません。 |
仮説、検証、実証。その先にあるもの。
また、相場の世界においては「仮説」や「検証」の先で「実証」された結果が、必ずしも「絶対的な答え」になるわけでは限りません。
仮説を立て、それを検証し、想定する結果が実証されても、そのプロセスが今後も再現され続ける保証はないため『決して、それが絶対的なものと過信するべきではない』というのが私の考えです。
故に、有効なテクニカル分析の基準を確立するには、
| 仮説 → 検証 → 実証 |
といったプロセスを過去の相場を対象としたバックテストはもとより、リアルタイムに動いていく相場に対しても繰り返し行う必要があります。
そして、その検証結果が、いわゆる『実証』に至らなかった時(想定した値動きが伴わなかった時)こそ、先立つ仮説のどこに改善の余地があったのかを追求し、言わば、その「敗因」を徹底的に洗い直す必要があるわけです。
当然、その際には「実証に至った時(想定した通りの値動きになった時)」との「比較」を前提とする視点が有効となる場合もあるため、
・何故、勝てたのか(勝因の追求)
・何故、負けたのか(敗因の追求)
これらが、より有効なロジックの確立に結び付いていく事になります。
ただ、その「仮説」の段階で『何故、そこで買うのか(売るのか)』という基準が、理論的な視点で「明確」になっていなければ、その「仮説」そのものを見直す事も改める事もできません。
そこで「テクニカル指標」を用いるのであれば、
『その指標と値動きの因果関係をどう仮定しているのか』
といったものが、その出発点となる「仮説」であり、仮説、検証、実証のプロセスは、そこから始めなければならないという事です。
▼ テクニカル指標の理論、成り立ちについての考察。まとめもしも本気で有効なトレードルールや売買の基準を、いわゆる「テクニカル分析」を前提とする形で確立したいのであれば、 ・自分自身がその合理性に納得できる指標を用いる事 これらを徹底するべきあり、これらを徹底して行っていく事こそが、その「正攻法」と言えるプロセスに他ならないと思います。
|
以上、本講義ではテクニカル指標の理論、成り立ち、計算式、その背景などを捉える視点についてを私なりの視点で言及させて頂きました。
今回のテーマに関連する講義も他に幾つかございますので、よろしければ併せて参考にしてください。
>テクニカル分析の本質とそれに基づく有効なトレードルールの条件について。
>テクニカル指標の有効な組み合わせを導き出す原則について。
本講義の内容が、少しでも今後のあなたの資産運用のお力添えになれば幸いです。
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。